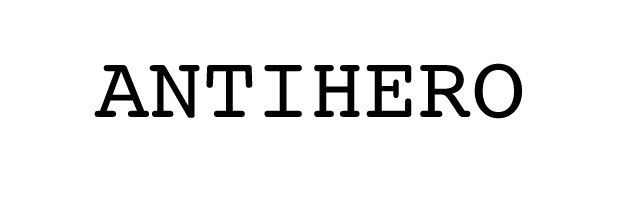朝起きて、胸のあたりから「ボゴゴッ」と水中で息が漏れるような音が聞こえた瞬間に激痛が走り、呼吸が出来なくなった。とりあえずその日は仕事に行き、退勤時間になるやいなやそのままの足で病院に向かうと、レントゲンを見た医者は「気胸ですね」と僕に告げる。
気胸とは簡単に言えば肺の周りから空気が漏れて風船のようなものが出来、肺を圧迫して呼吸が出来なくなってしまう病気だ。軽度であれば胸にチューブを挿してその漏れた空気を抜いたり、自然治癒で治したりするのだけど、僕の場合は心臓まで圧迫されているという危険な状態だったためすぐに手術が必要とも告げられた。
その日のうちに胸にチューブを差し、肺の中に溜まった水や漏れた酸素を抜く作業が終わり次第手術を始めるとのことで、一ヶ月ほどの入院を余儀なくされた。とりあえずは会社に入院した旨を伝え、手術の日まで静かにベッドで安静する日々を送ることになった。
肺に関わる病気を患う人は、二種類いるように思えた。高齢の方か、僕と同じ年ぐらいの二十代の若者。その中間ほどの年齢の方は非常に少なく思え、事実僕がいた病室と、その隣の病室も、その隣またの病室も、僕を覗いては恐らく齢六十を超えているであろう人ばかりだったのだ。
そうなればある程度「死」を覚悟した人も少なくはなく、気胸だけにとどまらず肺気腫や気管支炎などで亡くなられる人もいる。事実、僕がLINEで友人に「●●病院に入院した」と伝える(遠回しにお見舞いに来いという意味を含めている)と、「そこは気をつけろ」と友人は心配の言葉よりも先に僕に投げかけたことがあった。どういうことかと聞くと、友人は淡々と啓蒙活動でも行うかのように僕にこのような文章を送ってきた。
「その病院は俺のおじいちゃんが入院していたんだけど、医者に殺された。お前と同じ気胸で、手術をすることになって、その後逝ってしまった。手術の内容に不審な点があったし、俺の爺ちゃんは薬漬けにされて殺されたんだ。俺の家族もその病院を訴える準備を進めている。お前も気をつけろ」
気をつけろってなんだ。逃げろってことか。そう思いながらも「わかった」とだけ返信はするものの、病院とはそういう場所なのではないかと思っていた。僕が入院した病院は住んでる町の中でもかなり大規模な病院で、死者が出ることだって珍しくはない。ケースバイケースでそういうことだって起こりうるし、仮に僕がそうなって死んだとしても、僕の家族や友人はそれで病院を責めるような人間も少ない。そういう点では、安心していた。
しかし、昔誰かに聞いた話で、このような話を聞いたことがある。入院生活を長く過ごして病院で亡くなったものは、病院に残り続けると。なぜなら、病院は手術や病で亡くなった者を供養する場所ではないからだ。冷たい言い方をすれば供養は遺族などが行うもので、病院で亡くなったものに対するケアに病院は対応できない。病院は「生」に向かい「死」と戦うものの場所であるため、既に亡くなってしまった者のケアまでは対応が出来ないのだ(むろん遺族や余命が発覚した者に対する精神的なケアは必ずといっていいほど行う)。たまに病院の周辺で像の前にお供えものが置かれていることがあるが、それは土地柄によるものだったり患者の早期回復などと言った目的のものがほとんどだ。
「だから、病院はたまにヤバい奴がいるんだよ。すごく悲しいことなんだけどさ」
誰かの言葉を心の中で反芻させる。しかし入院した頃の僕は色々なこと(テキストの文章参照)を既に経験していたから特に恐怖心も抱かなかった。僕の入院生活は順調そのもので、喫煙が出来ないことに対するストレスは否めなかったものの、iPhoneを病室で使っていいと許可が降りてからというものの暇を潰すことも出来て快適と言える入院生活だった(当時は「なんだこの監獄みたいな場所」と思っていたけど)。
ふと、夜に目が冷めた。機械がブゥゥゥン……と小さく呻く音と、同じ病室にいる者達の寝息がきこえる。寝ぼけ眼でiPhoneを手に取ると、深夜の二時だった。尿意を催した僕は乱れた入院服を整えて、ベッドから降り、病室に向かう。
ナースステーションとトイレから離れた端の方に位置する僕の病室は不便ではあったものの、深夜も機能が停止しないナースステーションから離れているという点においては静かで快適とも言えた。しかしこうして夜間にトイレに行く際の灯りは少なく、不気味な雰囲気を漂わせている。その日、昼の友人とのLINEのこともあってあまり前向きな気持ちになることも出来ず、足早にトイレに向かうことにした。
用を足し、僕はトイレから病室に向かう。ちょうどトイレと病室の中間あたりの場所で、
「どこにいくの」
耳元で、はっきりと聞こえた。老人の声。男性か女性かもわからなく、酒やけしたような声だった。
びくっとして、振り返るが誰もいない。聞き間違いか、と思いながらも踵を返し、自分の病室のドアをじっと見据えて歩き始めようとする。
が、気配がする。恐怖心から来た気のせいかもしれないけど、この廊下に誰かがいる。他の病室の人がトイレに向かっているのだろう。もしくは看護師がいるのだろう。そう心に言い聞かせて、僕は足早に病室に戻った。
翌日、何事も無く朝を迎えた。昨夜の声のことなど寝ぼけていただけだと自分に言い聞かせ、朝の採血を行う看護師に軽い口ぶりで僕は言ってみる。
「アレですよね。病院って結構怖い話とかあったりするじゃないですか。ここの病院ってそういうのあったりするんですか」
雑談でも始めるかのような口調で聞いてみた。すると一瞬採血の準備を進めていた看護師さんの手が止まり、少し怯えた目で僕を見る。が、すぐに普段どおりの顔に戻り、僕に返してきた。
「まさかぁ。ここはそういうの無いですよ。大きい病院ですし」
嘘だ、と思った。大きい病院なんて根拠にならない。それどころか、その方が死者は多く現れる確率は高いのではないか。そういう気持ちで僕は口ぶりを変えずに言葉を返す。
「じゃあ昨日のは気のせいかな」
「昨日の?」
完全に採血をする手が止まった。血の気が引く、といった面持ちで看護師はそう聞き返す。
「いえね、昨日トイレに言ってるときに何か聞こえた気がするんですよ。ナースステーションの方からでもなかったし、何て言ってたかわからなかったけど、たぶん寝ぼけていたんですかね」
ある程度濁したほうがいいと思い、あえてそのような言い方をしてみた。すると看護師は採血を始めながら、僕の目を見ずに言った。
「ホントはね、こういうのは患者さんが不安になるって言うからあまり言わないようにって言われてるんですけど、そういうのってあまり返事しないほうがいいみたいですよ」
「返事?」
「そうそう。そういうのって見える人と見えない人っているじゃないですか。ああいうのって見える人をひたすら探しているらしいんですよ。だから返事をしてしまったら、って話を聞いたことがあるんです。私はそういうの信じないんですけどね」
「あぁ、なるほど」
「まぁ」採血を手際良く終えた看護師は道具を片付け始め、「この病院にいるってことは私が会ったことある人でしょうし、怖くはないですよ」
「会ったことあるというのは」言葉に詰まり、続きを言うのは辞めた。恐らく看護師は「生きている間に」という言葉をあえて付け足さなかったのだろう。その様子を察したのか、看護師は少し笑顔で「そうです」とだけ言って、病室を後にする。
その夜、また同じ時間に起きた。1分の狂いも無く目が覚めた。頭の霧が晴れず、誰かに起こされたような感覚で上体を起こす。尿意は催していない。なぜか眠る気にもなれずにボーッと布団を見つめ、次第に尿意を催したため誘われるように僕はトイレに向かった。同じ廊下、同じ道程で。
その日も廊下には誰もいない。非常灯の緑色の灯りが弱々しく照らしていたり、足元の電灯が廊下に反射していたり、遠くの曲がり角の向こうではナースステーションの灯りがこぼれている。しかし廊下は薄暗く、闇とまでは言わないものの目覚めに歩くには暗いと言わざるを得ない暗さだった。
トイレの灯りが眩しい。用を足している最中は光が眼球を刺して脳を無理やり奮い立たせるような強引さに不快感を感じ、眉間にシワを寄せながら僕は手を洗い、トイレを後にする。暗闇に慣れた目がまた元に戻り、行きよりも帰りのほうが暗く感じる。行きはよいよい、帰りは怖い。まさにその通りだった。
ペタッ、ペタッと、僕のスリッパの音だけが反射する。他に足音は無い。が、不思議と何かの気配は感じる。これもまた恐怖心から来る気のせいだと思い、僕は下っ腹にぐっと力を込めて病室に向かった。誰かに見られている。それもただ通行人を見るような目ではなく、何らかの目的があったうえで凝視するような視線。
病室の前に着いた。「やっぱり気のせいか」と僕がドアに手をかけようとした時、
「どこにいくの」
背筋が凍る。全身の血の流れを感じ、脳が熱くなって指先が冷たくなるのを感じた。体は不思議と震えない。うなじに冷たい息をかけられるような恐怖を感じた。返事をしてはいけない。そう心の中に言い聞かせるが、体が動かない。
どうすればいい、と必死に自分に言い聞かせるが、正直考える時間があるのかどうかもわからない。とりあえず、僕は相手が害のあるものとは限らないという考えを巡らせた。そもそも、コレは様々な話を聞いてきた僕の記憶と疲れによる幻聴かもしれない。だから、
「寝ます」
端的にそう答えた。掠れるような小さな声。しかしその瞬間、空気は一気に重くなった。病院中の視線が僕に集中するような緊張感のようなものを感じ、全身の皮膚がぴりっと痺れる。一気に気配が近づくような感覚。これは、本当にマズいかもしれない。そう思った僕は声も出ず、一刻も早く自分のベッドで毛布に包まろう。その一心でドアを勢いよく上げた。しかし病室は廊下よりも暗い。暗闇とかではなく、黒。何も見えなかった。しかし、それが大きな黒い影だということに気付いたのは恐らく直感と、恐怖心で頭が冴えていたからだろう。
思わず体が凍りつく。じっと見つめ合うような時間が永遠のように続いた。実際のところは一分も無い時間だったかもしれないけど、僕にとっては凄まじく長い時間に思えたのだ。その直後、影の中から篭った声で、
「……ちがう」
とだけ聞こえた。その瞬間に影は消えて、僕は恐る恐る歩みだし自分のベッドに辿り着いた。横になって深呼吸し、毛布を被って眠る。そのまた次の日も何事も無く朝を迎えることが出来、僕の心臓は完全に落ち着きを取り戻していた。
昨夜見たあの影が言った「ちがう」とはどういう意味だったのだろうか。きっと何かを探していて、僕がそれに該当しないとされたのだろう。
この事を看護師に言うわけにもいかず、ましてや友人などに言えるわけもなく、僕は静かに心の中にしまいこんでいた。しかしこうして自分のサイトを持ち、これを話す機会を得ることが出来るようになったため、今回の出来事を話すことにした。
あの時、もし僕があの影にとって違わない存在だったら、僕はどうなっていたのだろう。今でもそれを、時々考える。